第20回 難民映画祭 レビュー①
ある日突然「難民」と呼ばれるようになった人たちにも、かけがえのない人生があることを知ってほしい。
そんな思いから、国連UNHCR協会主催で、日本初の「難民」に焦点をあてた映画祭として2006年に始まった難民映画祭。
第20回となる今年の開催期間は、2025年11月6日(木)~12月7日(日)。
というわけで、現在絶賛開催中です。
UNHCRと国連UNHCR協会について
国連UNHCR協会は、国連の難民支援機関である UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) の活動を支える日本の公式支援窓口です。
UNHCRの活動資金は、各国政府からの任意の拠出金と民間からの寄付金に支えられています。
より広く民間からも支えようという機運が世界的に高まり、日本では2000年10月に、特定非営利活動法人として「国連UNHCR協会」が設立されました。
私は「国連難民サポーター」という形で、毎月定額の寄付を始めて約5年。
子どもが小学校高学年になり、学童に通わなくなったタイミングで、学童にかかっていた月額金額をそのまま寄付にまわそうと家族で話して決めました。もちろん、寄付控除の対象です!
今回、このUNHCR協会からの案内で知ったのが、難民映画祭。
中学生になった子どもと一緒に観ようと思い、オンラインで鑑賞を申し込みました。
鑑賞方法と参加のしかた
東京・大阪では劇場開催もありますが、基本はオンライン鑑賞なので、誰でも・どこからでも参加できます。
- オンライン開催期間:2025年10月7日(火)10:00~12月7日(日)18:00
- 参加費:若い人や学生さんが参加しやすいように無料鑑賞枠あり
- 寄付つき鑑賞:1作品 2,000円~、8作品まとめて 5,000円~(寄付額は自由設定)
ちょっとしたランチ代や映画代と思えばお安いですし、普段日本で難民問題に触れる機会もあまりないので、少しでも興味がある方、特に小学校高学年以上のお子さんがいるご家庭にはぜひおすすめしたいです。
寄付について話しながら家族で映画を観る――そんな時間が、きっと貴重な学びになると思います。
やっぱり、これからの日本を支えていく世代の人たちに、もっともっと世界で起きている現実を見てもらいたいですよね。
鑑賞作品レビュー
バーバリアン狂騒曲(コメディ・フィクション)
舞台はフランスの田舎の村。
ウクライナ戦争の勃発をきっかけに、善意から「ウクライナ難民を受け入れよう」と議会で決定。
ところが、実際に村にやってきたのはシリア難民の5人家族でした。
アラブ人というだけで戸惑い、反発する村人たち。
偏見や価値観の違いが浮き彫りになり、難民としてやってきた家族だけでなく、村の中にも賛成派・反対派の溝が生まれていきます。
最終的にはハッピーエンド。
コメディなので重すぎず、初めて難民映画を見る人にもおすすめです。
ただし――フランス映画です(笑)。
これ大事。

際どいセリフやシーンが出てくるので、思春期のお子さんと観る場合は微妙な空気感になる覚悟が必要
我が家はその覚悟なしで観たため、気まずい瞬間を何度も乗り越える羽目に…。
不倫・浮気・巨大なソーセージ(!?)、そしてベッドシーン的な描写もあります。
もちろん下着はつけていますが、ちょっとお下品で何とも言えないシーンが想像以上にあります。性愛も全て日常生活の一部、ということでしょうか。
でもそんな部分を差し引いても、偏見や差別、文化の違いに向き合う人間ドラマとして見ごたえがあります。
笑いながらも、考えさせられる一作です。
見えない空の下で
こちらは一転して静かなドキュメンタリー。
ウクライナ戦争開始後、地下鉄駅で暮らす少年を追った作品です。
日光を浴びることもできず、友達もいない。
「死」がすぐそばにある日常の中で、少年が出会う少女とのたわいない時間、家族とのやり取りが淡々と描かれます。
印象に残ったのは少年のこの言葉。
「マスコミが戦争初日にしか興味がないのはなぜ?
どうして2日目や5日目には興味がないの?」
2022年に始まった戦争。
もう3年が経つ今も、終わりは見えません。
1年、2年と経つうちに世界の関心は薄れていきますが、現地ではむしろ今の方が深刻かもしれない。
そんな現実を、静かな映像が伝えてきます。
一日も早く戦争が終わり、彼らが元の生活を取り戻せますように。
心からそう願わずにはいられません。
「無関心」でいることが一番の問題
ウクライナだけでなく、世界中で多くの人が家や家族を失い、安全な場所を求めています。
もちろん、個人の寄付で救える範囲は限られています。
でも、知ることから始まる一歩は、きっと誰にでもあります。
日本は難民の受け入れ数が非常に少ない国です。
ただ、ただ数を増やせばいいという話ではなく、賛成にも反対にもそれぞれ理由があると思います。
大切なのは「自分には関係ない」と思わないこと。
こうした映画祭をきっかけに、一人でも多くの人が「難民問題」を遠い世界の出来事ではなく、自分と同じ“人間”が直面している現実として感じてくれたらと思います。
我が家は8作品すべてを鑑賞予定。
また次回、他の作品のレビューも書きたいと思います!
難民問題に興味のある方は、ぜひ 国連UNHCR協会の公式サイト をチェックしてみてくださいね。
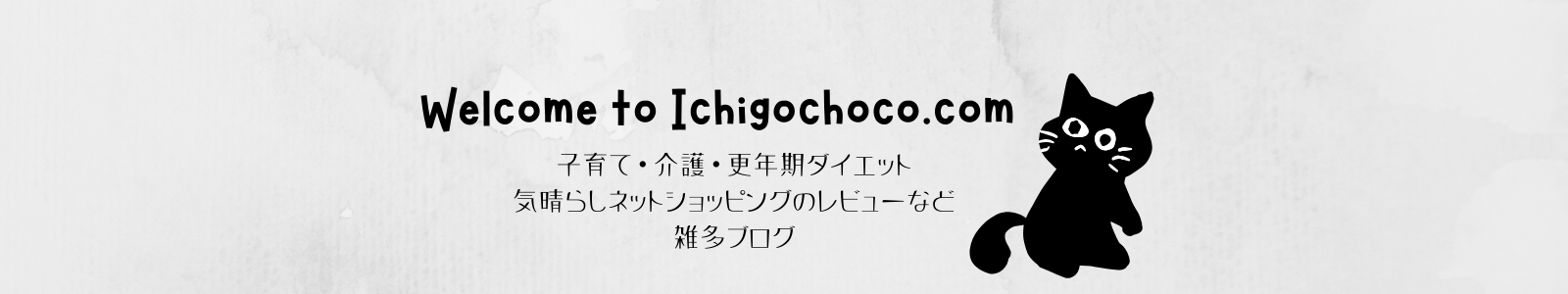
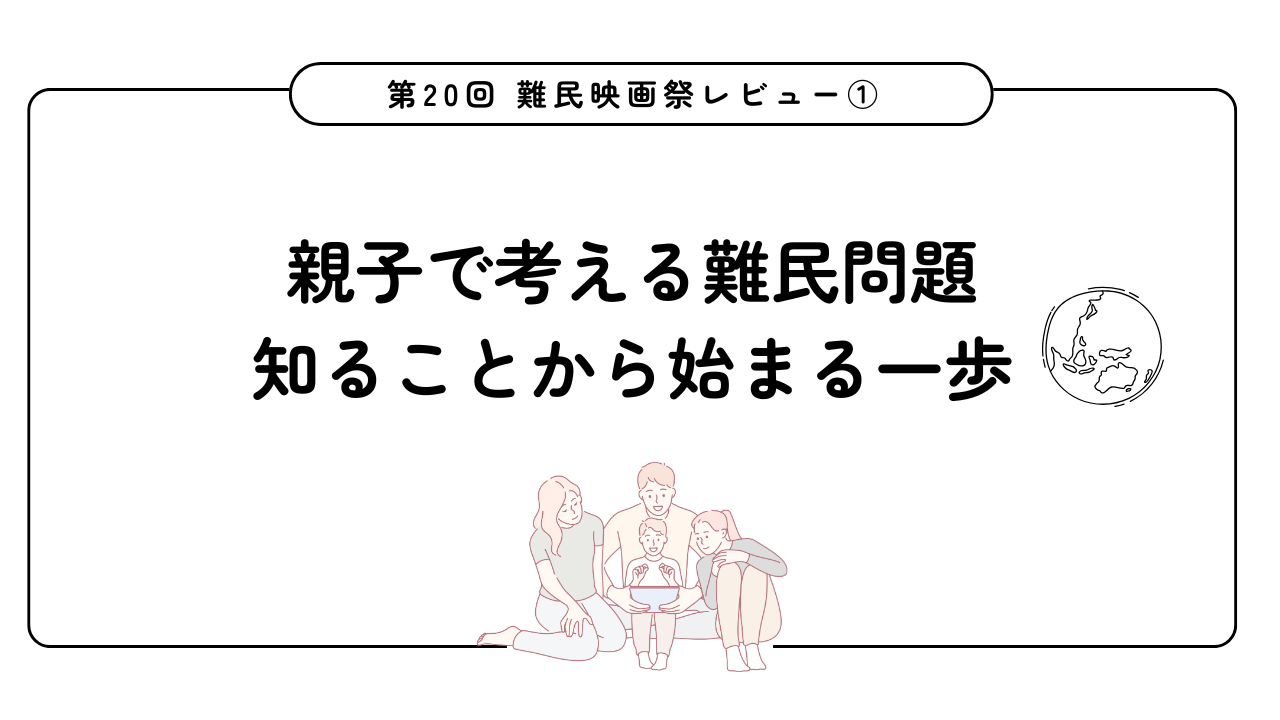
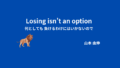
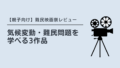
コメント