気候変動、地中海危機 —— 難民映画祭で出会った3つの物語を紹介。子どもと一緒に考えたことや、作品から感じた気づきを綴ります。
前回に続いて、現在開催中の難民映画祭で鑑賞した作品のレビューを書いていきます。今回の3本はこちら。
- ラジオ・ダダーブ
- あの海を越えて
- グッド・ライ(第10回 UNHCR 難民映画祭オープニング上映作品より)
さっそく、それぞれの感想をまとめます。
1. ラジオ・ダダーブ
25分の短編とは思えないほど、内容がぎゅっと詰まった圧巻の作品。観ている最中から、観終わった後まで、胸がきゅっと締めつけられる感覚が続きました。
ケニアのダダーブ難民キャンプで生まれ育った若い女性が、ラジオジャーナリストとして、難民たちの声と現実を世界へ届けようとする物語。
1991年にソマリア内戦の難民を受け入れるために開設された世界最大規模のダダーブ難民キャンプ。2011年頃からは、気候変動による干ばつや飢餓で避難してくる人々が急増し、受け入れ人数を大幅に超えた人口過密状態に。現在はキャンプに入れず、周辺地域で暮らす人も多いそうです。
難民=戦争・内戦・迫害というイメージを持っていた私にとって、
「気候変動が原因で故郷を失う人が今はもっと多い」
という事実は衝撃でした。
日本でも猛暑や台風の大型化など影響はあるけれど、「生活の継続が不可能になる」レベルの気候危機を日常的に感じている人は多くないかもしれません。子どもと一緒に観て、個人で比較的簡単にできることを少し話してみました。
- 歩けるときは歩く・公共交通機関を使い、車の利用頻度を減らす
- 服やスマホの買い替えサイクルを長くし、中古品も選択肢に
- ペットボトルの飲み物に頼りきらない
遠い世界の話に見えて、実は私たちの“日々の消費活動”が深くつながっているという気づき。消費の仕方を見直すことが、まずできる第一歩なんだと思います。
また、ダダーブには映画の主人公のように“キャンプで生まれ育ち、大人になる人たち”が多くいます。短期支援ではなく、居住地としての経済・生活基盤を整える長期的なサポートが欠かせないと強く感じました。
作品は25分と短く、気候変動の視点から難民問題を描いているため、小・中学生にもおすすめです。ちょうど今、ブラジルでは COP30 が開催中。親子で気候変動について話す良いきっかけにもなるはず。
こうしたニュースをきっかけに、子ども自身が“自分の意見を持ち、言葉にすること”ができるようになってくれたら嬉しいですよね。もちろん!将来の入試対策にもいいと思います!
2. あの海を越えて
ヨーロッパの地中海危機を扱ったドキュメンタリー。
結論から言うと、**子どもと一緒に観るのはあまりオススメしません。**とても丁寧で静かな語り口で進む作品なので、お子さんには少し退屈に感じるかも。大人向けです。
舞台はイタリア・ランペドゥーサ島沖。2013年、船が難破し155名が救助、360名以上が命を落とした悲劇は、日本でも大きく報道されました。
救助にあたった島民の証言ひとつひとつが静かに語られ、当時の状況がリアルに迫ってきます。そして、命を救われた人々がその後の人生を歩み、子どもが生まれ、命がつながっていくということ。助けられた人が、救助してくれた人を“Father”と呼び、今でも絆を保っているという事実に胸が熱くなりました。偶然にも救助にあたることになった島民の方々が、救えた命、そして救えなかった命と、今でも向き合って暮らしていることが伝わってきます。美しい断崖絶壁の島の風景、何もかもを飲み込んでしまうような海と空の深い青を背景に、命を危険にさらしてでも祖国から逃げざるを得ない人たちを取り巻く環境の辛さ、そして彼らを受け入れる島の人たちの優しさが、じんわりと浸み込んでくる、そんな作品です。
3. グッド・ライ 〜いちばん優しい嘘〜
最後に、どうしても紹介したい大好きな映画。今回の映画祭ではなく、過去作品より。
わが家が初めて“難民”というテーマに向き合うきっかけとなった作品です。

親子でみるなら、これが本当におすすめです
第二次スーダン内戦で難民になり、のちにアメリカへ移住した若者たち――「スーダンのロストボーイズ」を題材に、実話をもとに作られた作品。ロン・ハワード製作、リース・ウィザースプーン主演。第10回 UNHCR 難民映画祭のオープニング上映作品でもあります。
難民になる過程、キャンプでの生活、移住後の葛藤や文化の壁、家族の絆、そして新しい出会いや覚悟まで。コミカルな描写も織り交ぜながら、置いていかれがちな「リアル」をとても丁寧に描いた映画です。年齢を問わず観やすいのも魅力。
息子は小学4年生の頃から今の中学生まで、何度観ても飽きずに観ています。小学生の頃には理解しきれなかった部分も、成長するにつれて腑に落ちることが増えていくようで、これからも家族で毎年観ていきたい作品です。
おわりに
映画祭のタイミングだからこそ、より多くの人が映画を通して難民問題を知り、考えるきっかけになりますように。
難民問題に興味がある、映画祭をみてみたい、寄付はどうすればいい?そんな方は是非UNHCRのウェブサイトをチェックしてみください。
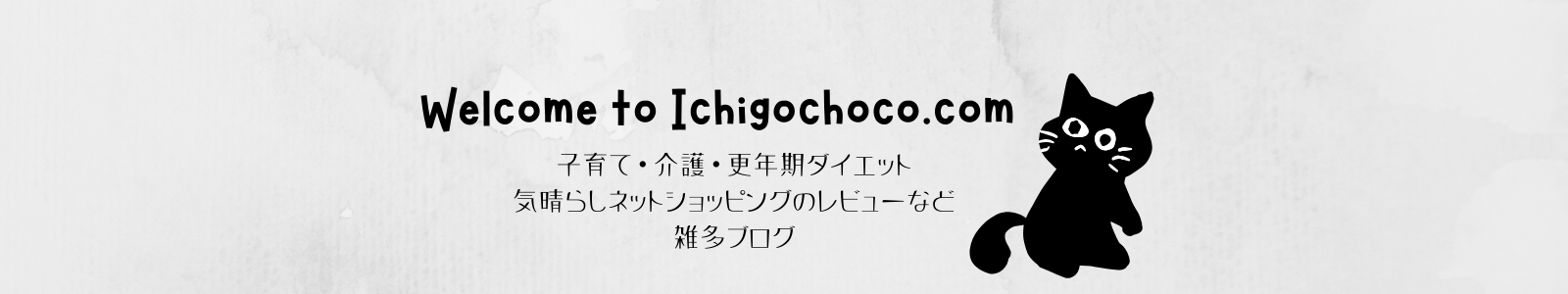
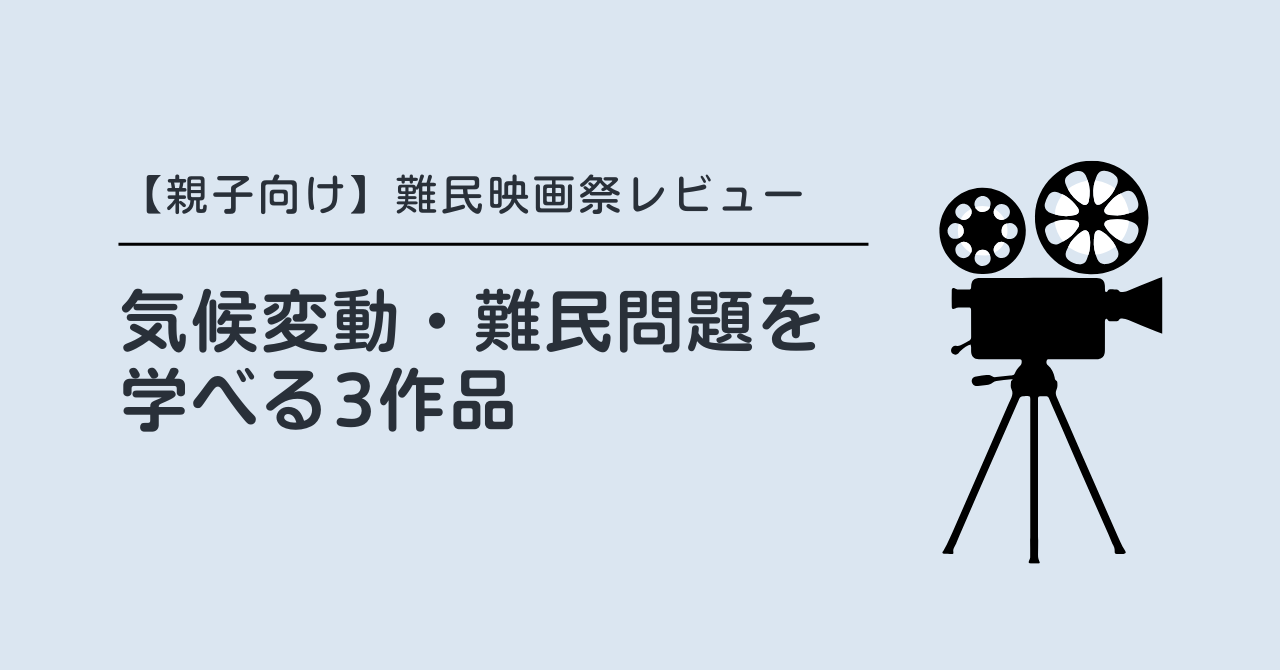
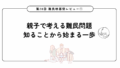
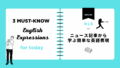
コメント